本記事の制作体制
 熊田 貴行
熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。
 熊田 貴行
熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

帯締めとは、着物を着るときに帯の上から結ぶ紐のことです。帯締めには、帯のかたちが崩れたりゆるんだりしないように帯を押さえる役割があります。
また、帯締めには装飾的な意味合いもあり、コーディネートのポイントとしても重要です。帯締めの色やデザイン、結び方などで着姿を大きく左右します。
ちなみに、帯締めを結ぶのは女性だけで男性の着物では使用しません。

帯締めは、大きく分けて「組紐」と「丸ぐげ」の2種類。また、組紐もかたちによって「平組」「丸組」「角組」に分けられ、種類によって格も異なります。それぞれ特徴を見ていきましょう。
平組は組紐の種類で、平らに組まれた薄いタイプ。無地やリバーシブルのほか、花柄や幾何学模様入りのものもあります。最も格が高くフォーマル向きの帯締めです。
平組にも組み方によって種類があり「高麗組(こうらいぐみ)」「綾竹組(あやたけぐみ)」「笹波組(ささなみぐみ)」「唐組(からぐみ)」などが代表的。幅が広いもののほうが格が高いとされます。
幅が三分(約9mm)の「三分紐」も平組の帯締めの一種ですが、こちらは一般的な帯締めよりも短くできていて帯留めをつけて使用します。もとは普段着用の格が低いものでしたが、最近は金糸や銀糸が施された豪華なものもあり、準礼装などさまざまな場面で使われるようになってきました。
丸組は文字通り丸く組まれた組紐で厚みがあります。「金剛組(こんごうぐみ)」「奈良組(ならぐみ)」などが有名です。
丸組は平組に次いで格が高いとされる帯締めで、厚手のものが格が高いとされます。振袖用の帯締めとして、パールなどの飾りがついた華やかな丸組も作られています。
角組は四角い断面の組紐です。平組や丸組よりも格は低くなり、小紋や紬、木綿などカジュアルな着物によく使用されます。
武官の冠に使われていたことから名称がついた「冠組(ゆるぎぐみ)」が代表的で、伸縮性に優れ締めやすいと定評があります。無地のほかグラデーションのものもあります。
丸ぐげは、綿を芯にして仕立てた筒状の帯締めです。組紐が帯締めの主流となる以前から使われていた帯締めで、かつては留袖や喪服などにも使用されていました。しかし、現在は礼装用には組紐の帯締めを結ぶことが多くなっています。
カジュアルな雰囲気のものも多く、アンティーク調のおしゃれ着のコーディネートに用いられることも多いです。また、子どもの着物にも丸くげがよく使用されます。
着物には格がありTPOに合わせて着分けますが、帯締めも着物の格に合わせて選ぶのが一般的です。
帯締めは、平組>丸組>角組の順で格が高く、平組なら幅が広いもの、丸組なら厚みがあるものが格が高いとされます。
結婚式など格の高い席で着用する黒留袖や色留袖には、白か白地に金糸銀糸の入った帯締めを締めるのがマナーです。平組で幅が広いものを用いるのが一般的ですが、丸組で厚みのあるものや丸くげを締めるケースもあります。
色留袖の場合は紋の数で格が変わるため、五つ紋以外なら淡い上品な色でも構いません。
成人式などで着用する振袖には、平組で幅広のものや丸組、丸ぐげでボリュームのあるものを合わせます。金や銀をあしらったものや飾りがついたものなどで華やかに装うといいでしょう。
フォーマルな場面では金銀をあしらった太めの帯締めを合わせるのが一般的ですが、それ以外は金糸銀糸が入っていなくてもOK。白や淡い色の帯締めで上品にまとめるのがおすすめです。
小紋や紬などカジュアルなおしゃれ着には、金糸銀糸の入らない細い帯締めを選びます。カラフルな色使いや個性的な組みの帯締めも映えるので、好みに合わせてコーディネートを楽しみましょう。
帯締めの色を選ぶ際、着物や帯の色から一色を取り、その濃淡の色を合わせて選ぶと色目がそろってまとまりやすくなります。
上品な印象に仕上げたいなら淡い色、パーティーなどでシンプルな着物や帯のアクセントにするなら主張のある強い色がおすすめです。

帯締めの結び方は数多くあり、とくに成人式の振袖では凝った帯締めの結び方アレンジも多く見られます。
帯揚げは、帯を結ぶときに帯枕を隠すために胸元の帯の上端に収めて飾る小幅の布小物です。帯締めとの色合わせが気になるところですが、定番で合わせやすいのは帯締めと帯揚げを同じ色や似た色でまとめること。着物や帯によっては野暮ったくなるケースもありますが、着姿全体がまとまりやすく失敗が少ないです。
一方、帯締めと帯揚げを異なる色にすると垢抜けた印象になります。単色ではなく、多色使いの帯締めや帯揚げを合わせるのもリズムが生まれてステキです。コーティネートに慣れたら次のステップとして挑戦してみるといいでしょう。
帯締めは、女性の着物に欠かせない小物。最近は海外製の安いものも売られていますが、締め心地など日本製のしっかりしたつくりのものにはかなわないという意見も多いです。せっかく和装を楽しむなら、きちんとしたつくりの本格的な帯締めでおしゃれを楽しみたいですね。
帯締めは組紐が一般的で、京くみひも、伊賀くみひも、江戸組紐など伝統工芸品も多いです。伝統の技が生きる帯締めのおすすめブランドを紹介します。
京くみひもの老舗メーカー「翠嵐工房」。伝統工芸士が生み出す手組の紐技術を現代に継承しつつ、伝統と現代の感性が融合した斬新なデザインを多く生み出しています。
正絹100%の締めやすく高級感のある帯締めに、きらめくパールやかわいい細工が施された華やかな帯締め。成人式の振袖にこだわりの帯締めを探したい方におすすめです。
房は撚り房で始末がラクになっているため、長く使用できます。
翠嵐工房
帯締め パール 花
井上工房は、三重県の伝統的工芸品「伊賀くみひも」のメーカー。着物雑誌にも度々掲載されています。伊賀くみひもは絹糸をおもな材料とし、組みの絶妙な味わいや華やかさが多くの人に支持されています。
すっきりと組まれた綾竹組の帯締めのうえに、ふっくらと大和組みを組みだした帯締め。美しく整然とした組目に上質さが漂います。
金糸が組み込まれていますが控えめで、おしゃれ着からセミフォーマルまで使えて便利。優しいカラーで着物の色柄に主張しすぎず上品に装うことができますよ。
井上工房
襲色遊び 金糸
江戸組紐の職人であった故・五嶋敏太郎氏により確立された「後藤紐」。皇室に献上する草履の鼻緒に使われた組紐第一号となったことで有名です。
素材にこだわり、上質な絹糸を丁寧に編み込んでいるため、締め心地が良く長い時間締めていても疲れません。デザイン・色使い・品質の良さから多くの着物愛好家から支持を集めています。
五嶋紐
正絹 帯締め 冠組
東京・上野の池之端に店舗を構える有職組紐の老舗「道明」。1652年の創業以来300年以上にわたり、手染め・手組みの伝統的な技法による組紐作りを行っています。
熟練の職人の手で絶妙な力の強弱、加減で生み出される複雑で繊細な紐は、機械による単調な力加減で作られる紐とは一線を画します。職人それぞれの個性が見られ、おなじ糸、組み方でもふたつと同じものが存在しない点も魅力。愛着がわく一本がほしい方におすすめです。
道明
冠組 両手先段「月白」帯締め
1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。
税込 16,500 円
★★★★★
(1レビュー)
4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。
税込 24,750 円
★★★★★
(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめランキング発表
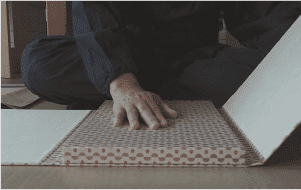
\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめ
ランキング発表
1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。
税込 16,500 円
★★★★★
(1レビュー)
4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。
税込 24,750 円
★★★★★
(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめランキング発表
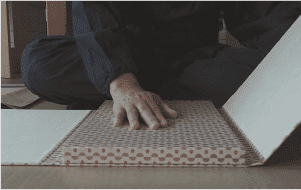
\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめ
ランキング発表