本記事の制作体制
 熊田 貴行
熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。
 熊田 貴行
熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。
「中国地方」は、鳥取県や島根県、広島県、山口県、岡山県からなるエリア。日本海に面している「山陰地方」と、瀬戸内海側に面している「山陽地方」があり、気候が異なります。中国地方では、和紙や漆器、筆のほかさまざまな伝統工芸品が作られています。各県の代表的な品をご紹介しますので、お気に入りのアイテムを見つけてくださいね。
鳥取砂丘で知られ、日本海の新鮮な海の幸が豊富な鳥取県には28品目の伝統工芸品が存在。「弓浜絣(ゆみはまかすり)」や「因州和紙」、「出雲石燈ろう」の3つは国の伝統工芸品に指定されています。鳥取県の伝統工芸品のなかから代表的な品を3つご紹介します。

「因州和紙(いんしゅうわし)」は、鳥取県の東部(鳥取市青谷町・佐治町)で作られる和紙の伝統工芸品です。因州和紙は、楮(こうぞ)などの天然の繊維に藁や竹などを配合した和紙を生産。
しなやかで酸化しにくい品として実用性にも優れ、東京浅草寺の「雷門」の大提灯や首相官邸の壁紙にも選ばれる逸品です。日本画や書道で使う画仙紙や、インテリア用品まで幅広いアイテムが作られています。

「出雲石燈ろう」は、鳥取県境港市を中心に作られる灯ろうです。原料には「来待石(きまちいし)」を使用。日本庭園に置いて使い、苔が付きやすい石をあえて選ぶことで、雰囲気のある灯ろうに仕上がります。
出雲石燈ろうは、大きめで存在感のある「立ち灯ろう」と、背の低い「座り灯ろう」の2つのサイズ。石と苔のコントラストが楽しめる逸品です。

「染物(筒書き)」は、鳥取県米子市で作られている染物です。筒書き染めは漁船で使う「大漁旗」を主に生産。筒書きを生産できる職人は、鳥取県の松田染物店1軒しか残っていない貴重な品です。
大漁旗に加えて、普段の生活に取り入れやすいトートバッグやエコバッグ、のれんなどの商品も製造。筒書きの技術で描かれた色彩豊かなデザインが特徴です。
「出雲大社」や世界遺産の「石見銀山遺跡」など、歴史的な見どころが多いことで知られる島根県には66種類もの伝統工芸品が存在。「雲州そろばん」や「石州和紙」、焼き物の「石見焼」の3つは国の伝統工芸品に指定されています。島根県の伝統工芸品のなかから代表的な品を3つご紹介します。

「石見焼(いわみやき)」は、島根県江津市や石見地方で生産される伝統工芸品。「飯銅(はんどう)」と呼ばれる赤茶色の貯水用の水がめが知られており、大きなサイズのものでは、大人の胸の高さほどある商品が作られています。
大型の焼き物だけではなく、急須や食器などの生活のなかで使えるアイテムも生産。耐久性や耐火性、耐水性にも優れた品で、さまざまなシーンで使われています。

「石州和紙」は、島根県の西部に位置する石見(石州)地方で生産されている和紙。耐久性の高い和紙として知られており、書道用紙や障子紙、インテリア製品などが生み出されています。
もっとも多く生産されているのは、「楮(こうぞ)」を原料にして作られた和紙。石州和紙の中でも特徴的なのが「石州半紙」で、通常は使わない楮の「あま皮」も一緒に使用することで、強度が高まり、容易に破れない和紙へと仕上げられます。

「八雲塗」は、島根県松江市で作られる漆器で、全国で2軒しか生産していない貴重な品。「色漆」や「青貝金銀粉」を使い文様を描いた後、「天然透漆」を重ね、伝統的な技法による研ぎ出す工程を経て作られます。
経年変化によって透漆の透明度が増し、文様が浮かび上がるのは八雲塗の大きな特徴のひとつ。現在では、無地の商品も生産され、使い続けることで鮮やかな発色が楽しめます。
本州の最南端に位置し、温暖な気候やさまざまな海産物が味わえる点が魅力の山口県には7つの伝統工芸品が存在。「萩焼」や「大内塗」、「赤間硯(あかますずり)」の3つが国の伝統工芸品に指定されています。山口県の伝統工芸品のなかから代表的な品を2つご紹介します。

「萩焼」は、山口県の萩市やその周辺で生産される焼き物。基本的に絵付けや飾り気のないシンプルな作風が特徴で、土本来の美しさが感じられる作品を多く生み出しています。
もっとも知られているのは「茶器」ですが、マグカップや食器など気軽に使えるアイテムも多く作られています。目が粗く吸水性をもつ萩焼は、炊きあがりや使い込むほどに風合いが変化することから、さまざまな表情が楽しめる点も魅力です。

「大内塗」は、山口県山口市やその周辺で生産される漆器です。「地塗り・下塗り・中塗り・上塗り」と、漆を繰り返し塗ることで強度が高まり、丈夫な点も特徴のひとつ。
色漆を用いた手書きのデザインも魅力的で、落ち着いた色合いの盆や椀などの品に美しい模様が描かれます。大内塗の技法を使った「大内人形(大内雛)」は、フォルムと表情がかわいらしい品。夫婦円満の象徴として親しまれています。
世界遺産の「厳島神社」と「原爆ドーム」で知られる広島県には14種類の伝統工芸品が存在。「熊野筆」や「川尻筆」、「宮島細工」「広島仏壇」「福山琴」の5つが国の伝統工芸品に指定されています。広島県の伝統工芸品のなかから代表的な品を2つご紹介します。

「熊野筆」は、広島県安芸郡熊野町で生産される伝統工芸品。世界でも最高レベルの優れた技術によって作られる筆は国内で80%以上のシェア率を誇り、海外でも高く評価されています。
熊野筆は軸が竹や木で作られ、毛の部分はウマやシカ、ヤギなどの獣毛を使用。72の工程を経て高品質の筆が出来上がります。書筆や画筆、化粧筆といった品は初心者から専門家まで広く使われている逸品です。

「宮島細工」は、広島県廿日市市(はつかいちし)宮島町で生産されている木工品。世界遺産の「厳島神社」とともに発展を遂げた宮島細工は、手触りの滑らかさと木目の美しさが特徴で、しゃもじや器、盆など生活に取り入れやすいアイテムも多く生産されています。
盆や柱などに手彫りで彫刻を施す「宮島彫り」や、ろくろを使用して茶たくや丸盆を作る「挽き物」など、どれも木目を際立たせる宮島細工の技法が存分に表現されています。
年間降水量が少なく。「晴れの国」とも呼ばれる岡山県には13種類の伝統工芸品が存在。「備前焼」と「勝山竹細工」の2つは国の伝統工芸品に指定されています。織物やうちわなどの品も作られている岡山県の伝統工芸品のなかから代表的な品を2つご紹介します。

「備前焼」は、岡山県備前市の伊部地区やその周辺で生産される伝統的工芸品。地名から「伊部焼」とも呼ばれる備前焼は、日本六古窯のひとつで、そのなかでも最古といわれています。
高温で焼き締めることから、金属に匹敵するほどの硬さが特徴の備前焼。釉薬や絵付けをせずに制作するため、素朴なシンプルさも魅力になっています。

「勝山竹細工」は、岡山県真庭(まにわ)市周辺で生産される竹細工製品です。「そうけ」と呼ばれる、かごやざるが主な製品。穀物を入れる「大ぞうけ」や、米をといだ後の水切り用として使う「米あげぞうけ」など、大きく分けて4種類が存在します。
加工していない青竹を使うため、素材の素朴さと職人の技による美しい仕上がりが魅力。現代の生活に合わせたパンかごや花かごなどのおしゃれな製品も製造されています。
広島県の「熊野筆」や、岡山県の「備前焼」など、数多くの伝統工芸品が全国的に知られています。中国地方の伝統工芸品はこちらをご覧ください。
1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。
税込 16,500 円
★★★★★
(1レビュー)
4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。
税込 24,750 円
★★★★★
(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめランキング発表
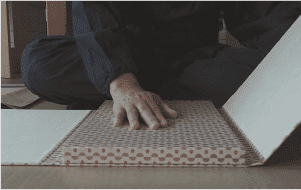
\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめ
ランキング発表
1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。
税込 16,500 円
★★★★★
(1レビュー)
4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。
税込 24,750 円
★★★★★
(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめランキング発表
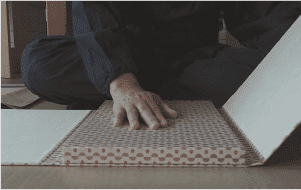
\ BECOS編集部が厳選 /
伝統工芸品おすすめ
ランキング発表